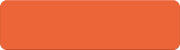『新版K式発達検査2020の概要
~子どもの発達段階を踏まえた保育とは~』
研修を開催しました
河内長野市内 こども園さま

~参加者の感想の一部をご紹介します~
・年齢に見合った環境作り(保育)の工夫が、子ども達の達成感、自信、意欲につながるということ。日ごろの保育を見直し実践していきたいです。
・検査内容の解説を聞き、子ども一人一人の発達を知るヒントを教えてもらいました。「このおもちゃはこの年齢(発達)に適している」など、子どもに関わる時のポイントなどを知ることができました。
・子どもが安心して遊べる場所、環境作り、玩具の準備などが大切だと改めて感ました。
・子ども達、周囲にいる仲間にプラスの声掛けを大切に過ごしていきたいと思いました。
・良いサイクル作り「温かみのある関係」の話が印象に残りました。
・子ども達が受ける検査なのに、内容を詳しく知らないことを不安に思っていたし、知りたいと思っていたので、研修を受けることができて嬉しかったです。
・「発達の最近接領域」を意識して保育に取組んでいきたいと思います。
・遊びの中で、発達につながる取組みをと思っていても、どうしても「ケガのないように」という考えが一番になってしまいます。少人数で遊べるコーナーなど、落ち着いて遊べる空間を作っていきたいです。
・検査内容を知って、「思っていたよりも難しいことができるんだ」、反対に「日々の保育では子ども達に難しいことだったんだ」と気づくことがありました。
・グループワークでは、自分のクラスの子ども達それぞれが、年齢相応の発達段階に達しているだろうか…と考え話し合いました。保育では個人差があることを踏まえ、その子に合った適切な援助を心掛けたいと思いました。
・研修で、詳しく子どもの発達段階を教えていただき、改めて気づくことがありました。子どもの発達段階を理解し、保育環境を整えたり、子どもへの言葉かけなども、もう一度考えてみたいと思いました。子どもの自己肯定感を高め、自信や意欲を育てていきたいと思いました。
・大人も子どもも保育を楽しみながら、遊びを通して色んな体験をしていきたいと思います。
・保育、子ども達との関わりの中で些細なことでもほめてあげたい。できるだけきれいな日本語で話してあげたいと思いました。